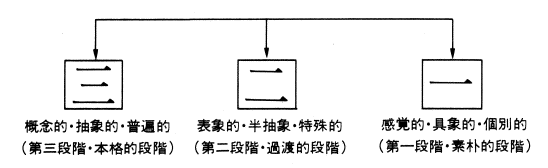
そんな形でこれまで言語関係の本に接してきて、そこで感じたのは、文字に関する考察の希薄さということだった。いうまでもなく人間の言語活動を直接に支えているのは音声と文字である。その音声についての研究に比較して、文字はいかにも閑却されている感があった。近代言語学の祖といわれるソシュールの言語理論が、音声言語のもを言語として扱い、文字はただ音声を模写するものとして従属的にしか考えていなかったことも、これまで文字がおざなりにされていた要因となっているのだろう。もちろん、文字の研究がまるで行われていないわけではない。言語学者の仕事にしろ、他の分野の人の手になるものにしろ、文字をテーマにした文章あるいは本もある。しかしそれらの多くは、さまざまな時代さまざまな国の文字を収集し、分類整理して文字の系統図を作りあげたという、いわば<資料作成>の域を出ていない。資料を整備する作業はそれ自体重要な仕事だし、大きな価値があるが、その作業の集積は直接に文字の理論を確立するには至らないだろう。ただ粗雑だった資料が緻密になっていくだけである。文字を理論的に解明するためには方法論的な視点がぜひとも必要なのである。
言語学者の中で、そういう視点を私たちに示唆してくれる人として、私はまず三浦つとむの名を挙げる。彼の著書「日本語はどういう言語か」の一部を引用してみよう。
いま絵画と言語とを用意して、それぞれに加工をほどこしてみましょう。たとえば石坂浩二のようなスマートな青年の肖像画をもってきて、その身体や手足を高見山のように太く変えてごらんなさい。肖像画を描いた画家は、表現を歪めたと怒るでしょう。しかし、言語表現の場合、吉川英治がペンで書いた原稿を持って来て、活字体で印刷しても、決して文句は出ないはずです。原稿の文字を、活字印刷しても、ネオンサインに変えても、電光ニュースで光らせても、意味が変わらないことはたしかです。ここから、絵画とちがって、言語の感性的なありかたは意味と直接の関係をもたないことがわかります。今度は、言語に手を加えて意味の変化する場合を見ましょう。点を移動させ(太/犬)、点を加減し(水/氷)、線を加減する(未/末、甲/申)などは、感性的にきわめて小さな加工でありながら、加工を許されていないのです。「木を売る」を「本を売る」に変えれば作者から抗議が出ます。これらの事実は、何を示すのでしょうか? 感性的なかたちの変化は、そのかたちが一定の種類に属するかぎりにおいて、その範囲を出ないかぎりにおいて自由であり、たとえ小さな変化であっても、そのかたちが他の種類に属するものに転化するような場合は許されない、ということです。言語の意味は、絵画の内容とちがって、感性的なかたちそのものにつながっているのではなく、そのかたちの他の一面に、すなわちそれが一定の種類に属しているという普遍的な面につながっているのです。この引用文で「言語」と書いてある部分を、「文字」に変えて読んでみれば、語られている内容は、より鮮明になってくるだろう。文字デザインの仕事をしている人ならば経験的によく理解していることである。引用文でゴシック体になっている「一定の種類に属しているという普遍的な面」とは、いわゆる<字体>のことであり、また「感性的なかたち」というのは、いわゆる<書体>の様式に対応している。
ところで、それに関していくらか補足しておかなけらばならないのは「一定の種類に属しているという普遍的な面」というのが、直接に目で見、手で触れることのできるような実体的な存在ではないということである。それは観念的な存在であり、文字を表記するうえでの社会的な約束事=規範にほかならない。したがって<字体>とは、それ自体が単独に目に見えるような形で存在することはできず、「感性的なかたち」との統一によって、初めて具体的な存在となるものである。図式的にいえば<字体>(規範)+<様式>(感性的なかたち)=文字(書体)ということになろう。
この場合の<様式>は、かなり幅の広い概念で、私たちが日頃、エンピツでなぐり書きする文字の線のようなものから、精密にデザインされた花文字の点画、さらには板にきざまれた彫刻刀のミゾまで、要するに文字が私たちの目に映る際のすべての感性的なありかたを含むものである。こうした感性的な側面を抜きにして文字を語るのは片手落ちというべきである。<字体>は、あくまで文字表記のための規範であって、文字そのものではない。国語審議会が新漢字表試案を作る際、<字体>の示し方についての意見がまとまらず、便宜的に明朝体で<字体>を示した所似である。
現在、文字デザイン界とその周辺では<字体>と<書体>の概念の違いを、広く一般にPRすることに力を注いでいるが、その場合の概念規程として最大公約数となっているのは<字体>は文字の骨格で、<書体>はその骨格に一定の様式で肉付け、装飾をほどこしたもの、ということである。きわめて簡潔で、理解しやすい説明といえよう。しかし、その単純化の中に誤解を生む要因がひそんでいると思われる。先に述べたように<字体>とは文字表記の規範として、あくまで観念的な存在であり何らの実体概念ではない。
ところが<字体>を骨格と説明すると、何か実体的なもののようなイメージが惹起されるのである。例えば、デッサンによく利用されている石膏像を倒してこわすと、中には木やシュロで作った骨格がある。もちろん誰しも印刷された文字や、手描きの文字の「肉付け」をけずり取ると「骨格」が残るなどとは思わないだろうが、しかしそのかわり、明朝体(新漢字表試案!)や、日頃よく目にするゴシック体などを、すべての文字の「骨格」と誤解しかねないのである。したがって<字体>=骨格、<書体>=骨格に肉付けしたものという説明は、比喩としては妥当であるし、文字デザインの実際作業として、普通に行われているエンピツによる下書きとそれへの肉付けという現象の過程によく対応したものといえよう。しかしなお、それは、<字体>と<書体>の区別を経験的に熟知している文字デザイナーや、その周辺の人々に対して相応の説得力を持つとしても、一般に向けて普遍性として提示するには、前述のような誤解を招く不備があると思われる。
ここで私なりに<字体>と<書体>の区別と連関を、やはり比喩的に説明すると、次のようになる。
私たちは日頃、何気なしにクダモノという言葉を使うが、何かクダモノそのものといったものがあるわけではない。クダモノはミカンなり柿なり梨なりブドウなりの形でしか具体的存在とはならないのである。
このクダモノという部分を<字体>に、ミカンとか柿を明朝とかゴシックに変えて読んでみれば、おのずと<字体>と<書体>の区別と連関は見えてくる。
文字デザインの過程的構造
私たちが文字を覚え、身につけ、使いこなすようになる過程を想定してみたい。
これを現在の教育システムに沿って考えると、まず児童が最初に文字に目的意識的に真向かうのは一年生の教科書に刷られた教科書体である。ここでそれらの文字の読み方を教えられるのが第一段階。次にノートの大きなマス目の中に点線で印刷された文字をエンピツでなぞったり、先生が黒板にチョークで書く書き順に習ってひとつひとつの文字の姿を身につけるのが第二段階。そして、教科書に印刷された文字でも、黒板に書かれた文字でも一定の要件を満たしていれば同じ文字だと認識できるのが第三段階ということができる。いわば<字体>という名称は知らなくても、その内容を把握している段階である。
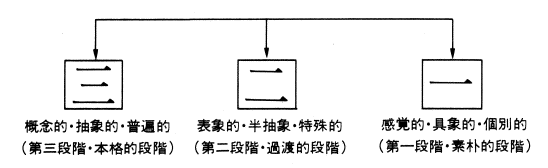
文字を覚えるのをこの図式で 一→二→三とのぼる過程とすれば、文字を書くのは三からおりる過程ということができる。しかし、こののぼりおりの過程は一→二→三、あるいは三→二→一の順をたどるとは限らない。例えば私たちが手紙を書いたりメモをとったりするのは<字体>に即座に具象的な形を与えるのだから三→一へ直接におりる過程であり、わからない文字を辞書で調べるのは一から三に直接のぼる過程である。
文字デザインは<字体>に即して進められるから三を出発点にしておりる過程だが、ここで二の過渡的段階が重要な意味を持つ。実作業に即していえば、この段階はいわゆるデッサン・下書きであり、へんやつくりなど文字の要素の長さや角度を決める段階ということができる。そして、それに墨入れ・修整をしたものが一つまり<書体>となる。したがって二は<字体>という概念的・抽象的な存在を、感覚的・具象的な<書体>に質的転換をさせるための契機として重要であるのみならず、デザイン文字にオリジナリティを与えるための過程でもあるわけだ。
以上、舌足らずな文章になってしまったが<字体>と<書体>に関する私なりの視点を述べた。筆を置くにあたって、文中の図版ならびにそれにともなう説明法は、認識論者・庄司和晃の「三段階連関理論」の直接・間接の応用であることを付け加えておく。