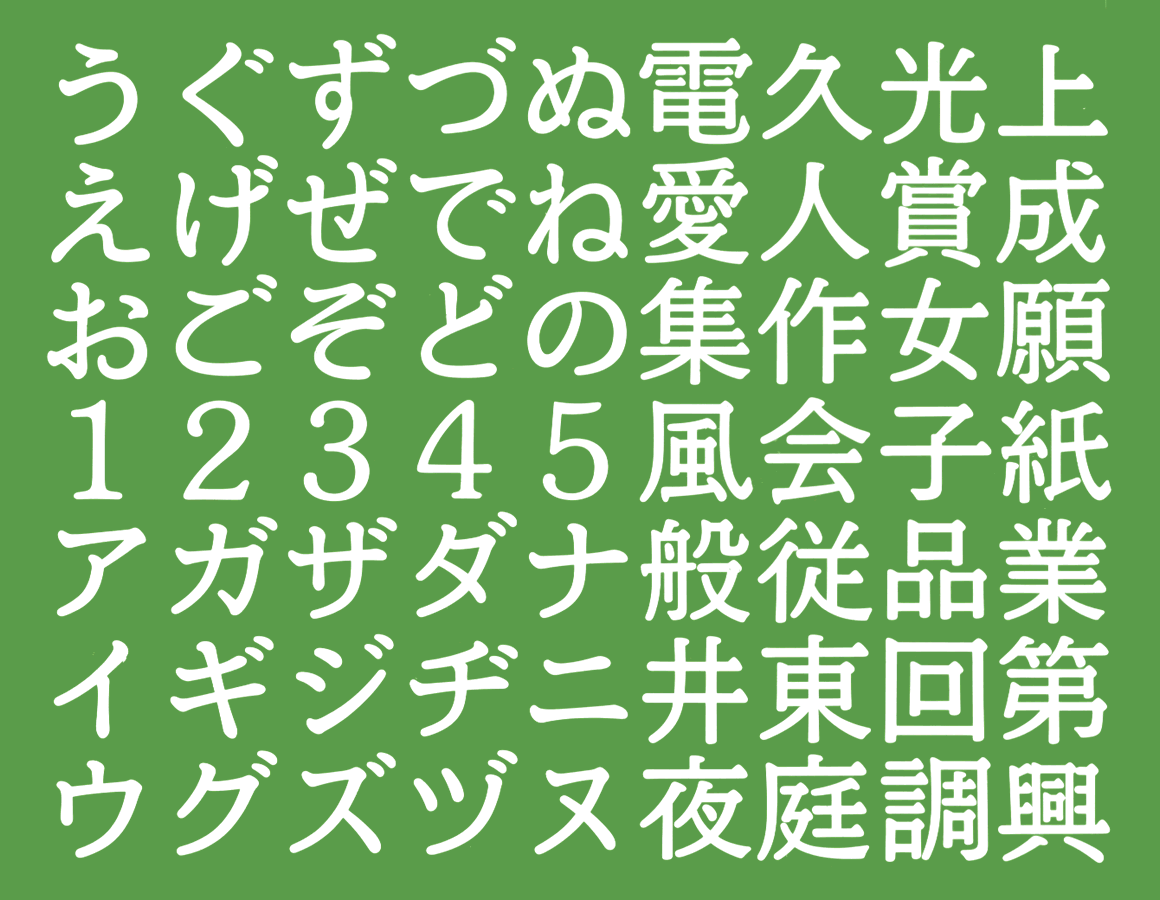
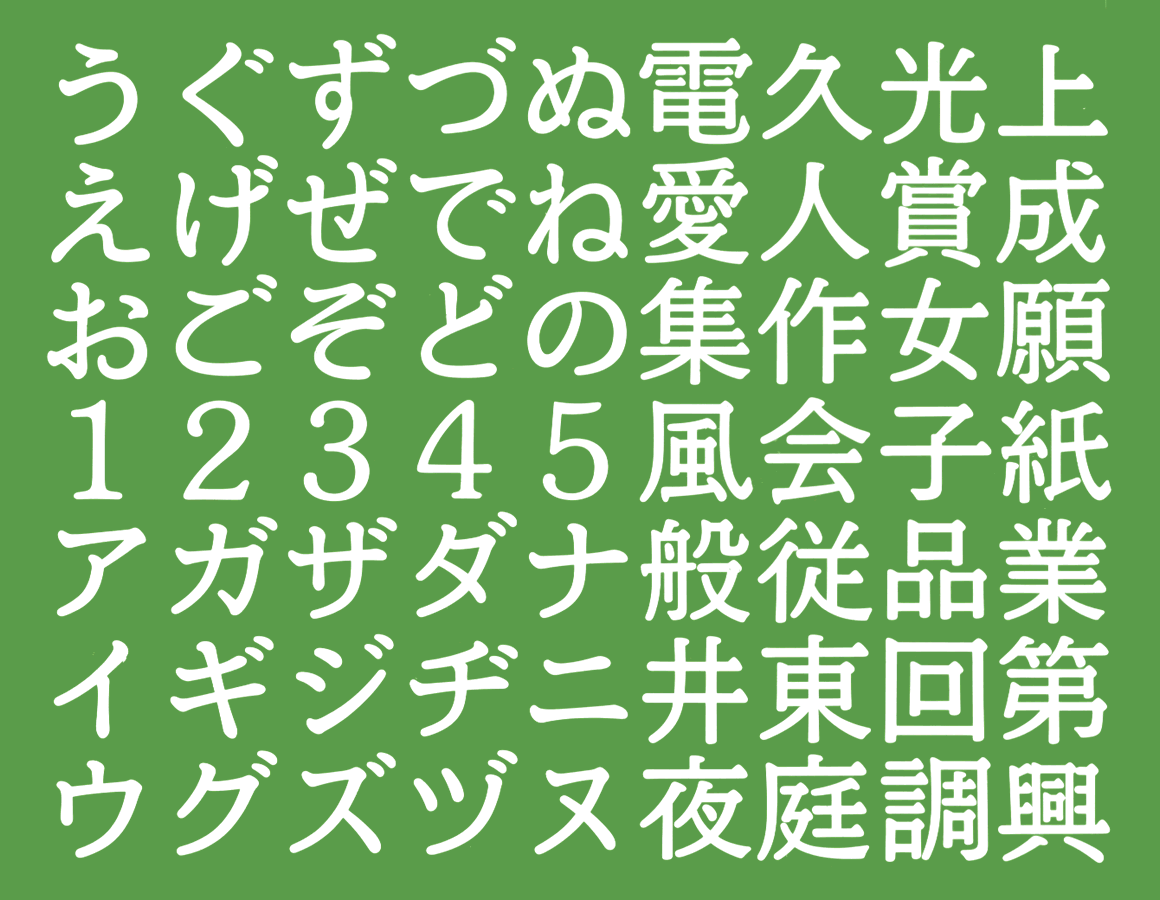
石井賞受賞*について
最近、自分の視力が衰えたのか、本文用の文字がやけに細く弱く感じだしました。それは活字から写真植字、凸版からオフセットへの印刷方式の移行が書籍の分野などにも拡がってきた結果なのかもしれません。
そして複写機などを中心とした簡易印刷機やファクシミリの普及など、文字伝達法はめまぐるしい速さで進化していますし、これから先も進化しつづけるでしょう。
しかし、それらの新しい伝達法に対応した書体はまだ開発されておらず、いつの時代にでも確実に対応できる書体があればいいなと考え、この書体を制作しました。
感性の時代などと呼ばれて、個人の感覚ばかりがちやほやされる今、機能を重視した私の地味な提案を推してくれた審査員の方々には感謝します。
出品した作品は、従来からの明朝体の特徴を生かしたまま、細いデリケートな線をなくし、エレメントの先端も、光学処理による形の変化がおこらないように丸くしたデザインですが、あくまでもイメージスケッチ程度の完成度なので、実際に製品になるときには、もっと手をいれなければなりません。
佐藤豊 「第9回 石井賞」受賞
写植システムのトップメーカー、(株)写研主催の「第9回 石井賞創作タイプフェイスコンテスト」(本年1月31日応募締切)で、同社から昨年発売された「ラボゴ」の設計などで知られる書体デザイナー、佐藤豊氏の作品(和文本文用)が、このほど最高賞の「石井賞」に輝いた。
同賞は、新人タイプフェイス(書体設計)デザイナーの発掘と印刷用新書体誕生の契機となることを願って、1970年より隔年でおこなわれてきた。単発のものは他にもあったが、継続的に開かれる一般公募のコンテストとしては、この分野ではわが国唯一。石井賞の名称は、写研創業者であり、幾多の障壁をのりこえて写真植字機を育てあげるとともに、いわゆる“石井書体”をつぎつぎと手がけ、また、55年完成の『諸橋大漢和辞典』(大修館書店)の、47500字にものぼる原字制作で名高い故・石井茂吉(1887―1963)の業績を顕影するために、この賞がもうけられたことによっている。
すでに今回で、9回目を数えるが、この間、第1回の「ナール」(中村征宏設計)、第2回のスーボ(鈴木勉)、第3回の「スーシャ」(同)、第7回の「ボカッシイ」(今田欣一)など、石井賞受賞の意欲作が商品化され、ぞくぞくと世に送り出されてきた。わが国の印刷用書体の多様化の進展に、同賞はおおきくあずかってきたといえる。
さて、佐藤氏の受賞作は、明朝体の魅力を生かしながらも、縦線と横線の太さにわずかの差しかなく、横線が通常よりはるかに太いのが特徴。ふところも広く、それぞれのエレメントの先端部に丸味をもたせた処理が、現代的な明快な骨格をつくりあげている。制作の意図を氏は、つぎのように語る。
「カラフルな印刷物がふえてきて、文字を白抜きにしたり、写真のなかに文字をおいたときなど、小さい字がうまく再現できないですね。たとえば、これまでの明朝では、横線がとんでしまったり、弱くなってしまっています。また一方で、複写機のコピーで印刷の体裁をとったり、ダイレクトオフセットといって、フィルムの版によらないで印刷ができてしまうシステムがたくさんでてきています。今回の書体は、こうした簡易な印刷方式や、新しい伝達方法にも文字の品質がおちないようにデザインしました」。前述の本書体の特徴は、だから、光学処理や、“疑似”印刷による形の変化、線質の劣化に対処したものであったわけだ。印刷方式の変革とその流通状況を見すえて、それらに耐えうる条件を軸にデザインを提起したのは、佐藤氏の試みが初めてであろう。毎回、難航することの多い審査も、今回はすんなり、氏の作品に最高賞が決まったということだ。
佐藤氏はすでに、このコンテストで3度の佳作入選を果たしている。和文・欧文・約物(文章組みのなかで使われる記号類)の三部門にわかれている同コンテストだが、初めての入選(第4回)は和文で、漢字に比してかなを小さくしただいたんな設計。表意文字である漢字の印象を強めることで、可読性向上をねらった横組み用の本文書体だった。
つぎは第7回で、同じく和文。本文用と見出し用の2点で、旧来の活字のポイントが、大きくなれば線質も変えているように、それぞれ太さと骨格を変えて、ふたつがペアとなるようにした。筆記体風の筆意を生かした、くだけた表情がたのしい。
3度目(第8回)は約物だった。この約物部門は、審査員の杉浦康平氏の提案で中途から新設され、「約物の美学は、朗読や発声法などの延長上に展開する」と、いかにも杉浦氏らしい視点から、その機能のとらえなおしにおおきな期待を寄せてきたもの。
佐藤氏の作品は、ハートや形やクリップ、眼鏡、太陽、人の顔などをドットで表現した現代版絵文字風約物。「文章中にランダムにぶちこみ、従来の文字組版のイメージを破壊する」使いかたも考えられる、と勇猛果敢な提案もおこなっている。
しかし、最近話題を呼んだ「変体少女文字の研究」(山根一眞著、講談社)のなかで例示されているように、現代の若い女性の文章表記中には、ハート形や星形が句点の代わりに、多用されるなど、こうした絵文字記号がふんだんに使われている。氏の提案も、あながち破天荒なものではなく、時代の傾向に通底する新しいスタイルへの示唆を含んでいることに注目したい。
このコンテストで氏は、このように実験色の強い作風をおしとおしてきただけに、なかばあきらめの境地だったという。今回も「機能面からだけの追求で、いま、はやりの感性とか個人の感覚をほとんど抹殺したデザイン」だった。それだけに、石井賞の知らせにはよろこびの半面、「ぼくらしい個性のない作品なので、あれでよかったのかな……、と複雑な気持ちです」という。
レタリングを学んでいるときに、新書体ブームの呼び水となった「タイポス」(桑山弥三郎氏ら、69年発売)が登場し、外部のデザイナーでも書体をつくれることを知ったことが、この領域に進むきっかけになった氏だが、とはいえ、わが国は特殊な文字事情をかかえている。かな に加えて、常用漢字だけでも1900余字。写植の文字盤には、約5000字が必要だ。これだけの文字数を瑕瑾なく仕上げるまでには、気の遠くなるような持続力が求められる。
冒頭にあげた見出し用書体「ラボゴ」も、延べ6年を費やしたという。欧米の事情とは雲泥の差だ。ところが、まさに氏のいう「書いたものでなければわからない」作業量のわりに、まだ書体設計への認識は浅く、経済的な面でも充分むくわれていないのが現状である。氏が主宰するスタジオから、“書体の自費出版”をめざして かな のみの「わんぱくゴシック」など2書体を自力で発売したのも、なんとか書体デザインをビジネスとして成り立たせるための、ひとつの方途だった。
今回の受賞で、書体デザイン界に確とした地歩を築いた佐藤氏。これからもさらに、すばらしい書体をうみだしてくれることを願うとともに、この地味な分野への理解が高まるよう、その先導役も果たしてもらいたい。(野澤朔)
オーソドックスな字も書けるんですよ。
タイプフェイスデザイナー 佐藤豊氏 石井賞受賞
■今から4年前ですか、「タイポパワーズ」っていう若手のタイプフェイスデザイナーでグループを作ったんです。タイプフェイスデザイナー同志があまり行き来がなかったんですね。メーカーのお抱えみたいな感じで。お互い秘密をかかえてて、すごくつまんない状態だったんです。ヘンな競争してたり、横の繋がりが全然ない。それで同じ年頃のデザイナーをあつめて、メーカーや勤務先の壁を取り払ったグループを作って、「タイポパワーズ1984」という展覧会をやったんです。
最近、モリサワから「わんぱく」と「タイプラボ」というかな書体が発売されましたがその両書体は「タイポパワーズ1984」展で僕が発表し、2年前から自分で文字盤を作成して自主販売を続けていたものです。
写植のオペレーターや印刷会社にとって不便なことがありますよね、書体に関して。あるメーカーの機械を使っていると、普通はそのメーカーの文字盤しか使うことができない。それでもデザイナーは関係なしに、書体を指定して来るでしょう。そういう困ったことが実際にあるのに、あいかわらず1つのメーカーで出した書体は他のメーカーの機械にはセットできない、販売もしないという状況がある。これはほとんどの場合、書体の制作費と引換にメーカーがデザイナーから、権利を買い取っているからなんです。
カセットデッキだって、メーカーが違ってもテープはどこのテープでも使えるから、あれだけ普及して良い機械が開発されるんですよね。まあ文字盤の規格統一は無理としても、それだったら同じ書体がすべてのメーカーから出れば問題ない。
だから僕がこれ(わんぱくとタイプラボ)を作った時に権利は絶対に売らないと。制作費はどこからももらわずに自費で開発し、どこのメーカーにも独占されずに、最終的な権利は僕がもっていて、メーカーにはあくまでも文字盤の制作と販売だけしてもらう。そして売り上げに応じてロイヤリティをもらうという契約にしているんです。だから、「わんぱく」と「タイプラボ」は、モリサワでも売っているし、僕自身でも売っている。本当は、すべてのメーカーから販売して欲しいと思っているんですが…。
「わんぱく」と「タイプラボ」は、かな書体だからなんとか自費で制作できましたが、漢字を含めて何千字となるともっと困難になりますね。その間お金をもらわないでやるというのはかなり大変だけれども、いまのところ権利を自分に残すにはこれしか方法がないんですよね、実際。
■デザイナー、イラストレーターとか書くことを知っている人は、一生に1書体は自分の字が書けると思うんです。自分の気にいってる字がね。いつも印刷物なんかを見ててね、気にいってないとか、自分だったらこう書くなあとか。そういう面がある人だったら、1書体は書けると思う。そういう自分の字を追及していってる人もいますね、毎回似たような字を書く人が。僕は、そうでなくって1回出品してしまったら、そこでやめて、次は新しいものを考える。そういう意味では逆にプロだと思っているし、目的に合わせて書き分けられるつもりでいるんですが。
今回の書体(第9回石井賞タイプフェイスコンテスト第1位受賞作品)は、デザインが表に見えないというか、地味な字だったでしょう。真面目で、オーソドックスで。でも他人が見ると、やはり僕らしい個性があるみたいですけれど。今までに世に出した「わんぱく」「タイプラボ」「ラボゴ」などの書体はすごくデザインしてしまった字だから。まあ、僕も書き分けられるんですよというのを知らせたかったのかな。
このコンテストでの制作意図には、ファクシミリやコピーに対応できるような書体と書いてはいるんですが、そういうものとはあまり関係なく、結果的に丸い柔らかみのある黒っぽい書体が新鮮だったというか。書体を作っている側としては、制作意図などには関係なく使われて欲しいんです。書いている人が本文用の字だといっても、見出しに使われたって嬉しいし。
最近、広告などでよく見るアンバランスに切り刻んだ字がありますね、あれは僕から見ると耐えられないのだけれど、広告デザイナーはああいうことをやって目を止めさせるんでしょうね。ですから文字を作る側がこう使ってくれといっても決められないですね。使う方は、目的に合わせていろいろ手を加えていってしまいますから。
いまコンピュータやなにかで、生活や身のまわりの様々なモノがキカイ的になってきています。そこでこういう柔らかい字が結構いいんではないかと思ったわけです。
■制作にかかった時間ですか……そうですね。物を創るという作業を時間では計るのは難しいですね。机にむかっている時間だけを言えばいいのかというと、そうでない部分がありますよね。
作業し始めた時間が必ずしも創作の始まった時とは言えない。それを作ろうかと決断するまでの様々な経験や、思考や出来事やなにかも創作には必要ですから。
生意気なことを言えば、僕の生きてきた35年間かかって作られた書体だということです。何を見てきたか、どういう生き方をしてきたか。そんな事で感覚って皆んな違ってくる筈です。
同じ課題が出て、僕がなぜ2位の人の字が書けなくって、2位の人が僕の字を書けなかったのか。それは、別々の生活や体験をしてきたからなんですよ。
いま、この書体が1番いいと思って今年出品したわけで、前回のコンテストではこの書体は書けなかったんだし、結局35年かかってやっと、このデザインにいきついたんでしょうね。
■一番楽しいのは、デザインを決める時でしょうね。ラフ・スケッチが。なんにもないところから、自分の形を作って、自分の好きな形になってきた時が1番楽しい。それをフィニッシュしていくと意外と思った通りにならなかったりして(笑)あとはもう修正作業の連続ですから、つらいですよ。
書と書体デザインっていうのは、絵画とイラストレーションの関係の様なものなんです。絵画を書く人は、多くの人に見せることを目的には制作していない。自己表現ですから。イラストレーションとかデザインは、それとは逆に複写して多くの人に機能しなければいけない。僕の書体も、使われて初めて役に立つ。だから文字盤にしたり、インレタのようなものにしてあちこちに使われて、デザインしたものが形になり、モノになり、見た人がそれなりのことを感じてくれれば1番うれしいですね。
書体は、イラストレーションなんかとも違って、作者を離れて全然しらない所で使われる。文字盤として知らない所へ売られていくわけでしょう。だから、本屋さんや広告なんかで自分の書体を見た時は嬉しいですね。この「ラボゴ」なんかは、少女マンガによく使われているんですよ。するとね、その少女マンガをつい買ってしまうんです(笑)
書体デザインの仕事をしていて一番辛いこと……、ん――。使われないことほど辛いことはないんじゃあないかな。
第9回 石井賞 佐藤豊
第9回 石井賞創作タイプフェイスコンテストの第1位石井賞が佐藤豊氏(1951年東京生まれ、69年日美レタリング教室研究科修了、現在、タイプラボ主宰)に贈られた。
同コンテストは写植用印刷書体の新人デザイナーの発掘などを目的に、(株)写研が隔年に主催しているもので、1位受賞作品などは実際に製品化され、現在までにも「ナール」書体などが普及されてきた。なお今回の応募作品数は165点で、2位は酒井正、木村千里+木村重忠の2組の各氏へ贈られた。
1位の佐藤氏は過去3回石井賞の入選歴もあり、クリップのイメージでデザインした欧文書体の「Paperclip」、コロコロとした見出し用書体「ラボゴ」などを世にだしている実力派。それだけに、今回の本文用書体での受賞は、今までの仕事のデザイン的なものと違って、オーソドックスなものが認められたことに喜びがある。
「仲間のものがみると、やはり佐藤らしいといわれるんですが、自分ではできるだけ個性をおさえて創った」という受賞作は、活字から写真植字、そしてオフセット印刷、と質的にも偏平化し、さらに貧相なワープロ文字の普及など気づかないうちに脆弱になっていく現在の印刷メディアの現況に、本来、言葉や文字のもつべき力強いマチエールを回復しようとする野心作で、明朝体の特性を生かしながら、光学処理の段階での質の劣化に対応するよう工夫されている。
「デザインはみなそうですが、一つの機能ですから、人の目に触れていってはじめて生きてくるわけです。自分が書いた書体が印刷物になったり、いろんな人に読まれていく、そういう過程で人の役にたったり、使われていったりするときが一番楽しいし、やりがいも感じます。
ですからどんないい仕事でも、世の中に出ていかないことにはどうにもならないんです」という佐藤氏だが、実際の文字盤となって製品化されるまでに2、3年の猶予を必要とする現実や、1つの書体が1社の独占になって、使用側の自由が狭められる現状などにはいろいろと不満があり、今までにも、「わんぱくゴシック」などを自費出版のような形で出したりと具体的な形で、“書体”のありようを模索してきた。
それだけに一つの書体が世の中に普及していくむずかしさもよくしっているわけで、「街かどで自分のつくった書体が使われているのを見かけると、少女マンガでもなんでも思わず買ってしまう」ほどに愛着もあるのだ。(編集部)
第9回 石井賞創作タイプフェイスコンテスト
第1位の栄冠を佐藤豊君(東京)が獲得。
たゆまぬ努力がみのって最高賞獲得。感性の豊かな仕上りや、太くしっかりした骨格に高い評価。
受賞を機会に佐藤君(日美・OB)から受賞作制作についてのアイデアや苦心、書体に対する日ごろの考え方、また、学習中のみなさんへのアドバイスを聞きました。
◎庶民的な感覚を追求
★いろいろな考えがあるとは思いますが、いま、あなたにとって書体とはなんでしょうか。
佐藤 答えになるかどうかわかりませんが、「書体」=仕事、つまり、書体をつくるのが仕事と思っています。
お高くとまっていない、親しまれる大衆的・庶民的な書体をつくるのを目的にしています。そういう仕事をもっともっとやって行きたいと思っています。
★こんどの受賞作品の制作に要した時間はどのくらいでしたか。
佐藤 そうですね。延べで3ヵ月から4ヵ月ぐらいだったと思います。正味は1ヵ月ぐらいでしょうかね。制作だけでなくチェックする時間も必要なので―(約150字)
★受賞作の制作と通常の仕事の調整は、どのようのしたのでしょうか。
佐藤 どちらかというとコンテストのほうを重視しました。時間が余ったらやろうと思ったらできないので。かなり、計画的にやりましたね。
★話は変わりますが、通常の仕事は、どういうものが多いのですか。書体の制作が中心だとは思うのですが―。
佐藤 そうですね。カタログやパンフレットなどのデザインや印刷物の版下の制作などをやっています。また、自分で開発した写植書体の文字盤を制作して販売しています。写植機も1台あります。
(佐藤君は、「わんぱく」および「タイプラボ」というゴシック系の書体を開発し、パンフレットやチラシの制作に使用したり、文字盤を製造し販売も行っています)
★その「わんぱく」「タイプラボ」という書体はどんな感じのものですか。
佐藤 「わんぱく」は、気どらない、ほのぼのとした表情で、「タイプラボ」は現代的なイメージで、ロゴタイプ感覚の書体といえるでしょうか。
◎伝達されるところに魅力
★書体にどんな魅力を感じているのでしょう。
佐藤 私がやっている書体をつくる仕事は、書道のように1点1品制作ではなくて、印刷物になって複製され、数多くの人の目に触れることになります。そんなところにとても魅力を感じます。
★受賞作品を制作するのにベースとなった考え方はどんなものだったのでしょう。
佐藤 一応、コンセプトのようなものは考えました。それは本文用として長い文章を組むときのために、読みやすさを主眼に、個性をやや殺した標準的なものをつくろうとしたことです。
★書体に興味を持ちはじめたのは、いつごろでしょうか。
佐藤 14〜18歳ぐらいのときです。日美のレタリング専科に入学しました。練習しないで、すぐ課題をつくってしまうクセがありましたね。仕事ができるようにもっとうまくなりたいと思って教室へ行きました。学園の受付ロビーに展示されている作品が、とても刺激になりました。
★現在、レタリング講座で学習している受講生にアドバイスを一言。
佐藤 途中で放棄しないで、飽きずに長く勉強を続けることが大切ですね。プロになろうと思ったら本気で、趣味でやる方はレタリングを楽しむのがいいと思います。